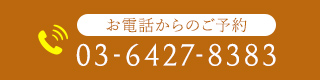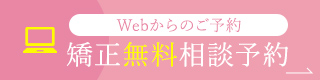口腔習癖と不正咬合:原因・影響・予防策について詳しく解説【 ⑦歯ぎしり(ブラキシズム)編】

「朝起きたとき、なんだか顎が疲れている」「歯がすり減っているような気がする」──そんな経験はありませんか?
実はそれ、睡眠中に無意識に歯を強く噛みしめている “歯ぎしり” が原因かもしれません。
歯ぎしりは、大人にも子どもにも起こりうる身近な癖でありながら、放置すると歯や顎、さらには全身の健康にまで悪影響を及ぼすことがあります。また、自覚しづらいため気づかぬうちに症状が進行してしまうケースも少なくありません。
この記事では、歯ぎしり(ブラキシズム)とはどのようなものか、そこから起こるリスク、そしてやめさせるための具体的な対策までを矯正歯科の視点から詳しくご紹介します。ご自身やご家族の健康を守るためのヒントとして、ぜひ最後までお読みください。
「歯ぎしり(ブラキシズム)」とは?
「歯ぎしり(ブラキシズム)」とは、主に睡眠中に無意識で上下の歯を強く噛みしめたり、こすり合わせたりする癖のことを指します。日中に無意識に歯を噛みしめてしまう「覚醒時ブラキシズム」もあり、どちらも歯と顎に大きな負担をかけます。
歯ぎしりは、大人から子どもまで誰にでも起こる可能性があり、「疲れやストレスがたまっているサイン」として現れることもあります。実際、仕事や人間関係などの心理的な要因がきっかけとなって、知らず知らずのうちに夜間の歯ぎしりが習慣化してしまうケースも珍しくありません。
一方で、歯ぎしりをしている本人は自覚がないことが多く、家族やパートナーに「音が気になる」と指摘されて初めて気づくことが多いです。放置すると、歯がすり減ったり、被せ物が壊れたり、顎の痛みが慢性化するなど、さまざまなトラブルに繋がるため、早期の対処がとても重要です。
「歯ぎしり(ブラキシズム)」が与える影響
歯ぎしりは一見すると無害な癖のように思えるかもしれませんが、実は口腔内だけでなく、全身にさまざまな悪影響を及ぼすことがあります。ここでは、歯ぎしりがもたらす代表的な問題についてご紹介します。
歯のすり減りや破損

強い力で歯をこすり合わせることで、エナメル質が摩耗し、知覚過敏や歯の欠け、詰め物や被せ物の破損が起こるリスクが高まります。長期間放置すると、歯が短くなってしまい、見た目や噛み合わせにも影響が出ます。
顎関節への負担

顎の関節(顎関節)には非常に大きな圧力がかかるため、あごの痛み、関節音(カクカク音)、口が開きにくくなるなどの症状が出ることがあります。これを「顎関節症」と呼び、日常生活にも支障をきたすケースも少なくありません。
肩こり・頭痛・首の痛み
歯ぎしりによる筋肉の緊張は、咀嚼筋(そしゃくきん)から首・肩・頭部の筋肉へと波及し、肩こりや緊張型頭痛を引き起こすことがあります。「歯ぎしりが原因で肩が重い」「朝起きると頭が痛い」と感じる方は、就寝中の歯ぎしりが関係している可能性があります。
歯並びや噛み合わせの乱れ
慢性的な歯ぎしりは、特定の歯に過剰な負荷をかけ、歯が移動したり傾いたりする原因になります。特に矯正治療中や矯正後に歯ぎしりが続くと、治療結果に悪影響を与えることもあるため注意が必要です。こうした問題に対しては、矯正歯科の専門的な診断と管理が非常に重要です。
「歯ぎしり(ブラキシズム)」をやめさせる方法
歯ぎしりの習慣は無意識下で行われることが多く、完全にやめるのは簡単ではありません。しかし、原因に合わせた対策を講じることで、症状の緩和や悪化の防止が可能です。ここでは、歯ぎしりへの具体的なアプローチをご紹介します。
マウスピース(ナイトガード)の使用

もっとも一般的な対策が、就寝時にマウスピース(ナイトガード)を装着する方法です。歯と歯が直接接触するのを防ぎ、歯の摩耗や顎関節への負担を軽減します。市販のものもありますが、長期的に使う場合は矯正歯科などで自分の歯に合ったオーダーメイドのものを作ることが推奨されます。
ストレスのコントロール
歯ぎしりの大きな要因の一つに「ストレス」があります。日中に緊張や怒り、不安を感じると、それが睡眠中の噛みしめや歯ぎしりとして表れることがあります。十分な睡眠、趣味の時間、軽い運動など、日常の中にリラックスできる習慣を取り入れることが、根本的な改善につながります。
日中の「噛みしめ」意識を高める
無意識に歯を食いしばっていることも歯ぎしりと同様の負担を顎に与えます。日中のふとしたタイミングで「上下の歯が当たっていないか」をチェックする習慣をつけましょう。正常な状態では、上下の歯は常に少し離れているのが理想です。
ボトックス治療

最近では、咀嚼筋(特に咬筋)にボツリヌストキシン(ボトックス)を注射し、筋肉の過剰な収縮を抑える医療的アプローチも注目されています。歯ぎしりの症状を緩和するほか、エラの張り感が気になる方にも美容的なメリットがあるとされています。専門の歯科または美容外科で相談が可能です。
噛み合わせの改善

噛み合わせのズレや不正咬合が原因で歯ぎしりが起きている場合は、矯正治療によって根本的な改善が期待できます。歯列や顎の位置を整えることで、噛み合わせが安定し、無意識の歯ぎしりも減少するケースが多く報告されています。専門的な検査を受けるには、まず矯正歯科でのカウンセリングがおすすめです。
まとめ
「歯ぎしり(ブラキシズム)」は、ただの癖では済まされない深刻な問題を引き起こす可能性があります。歯の摩耗、顎関節の痛み、歯並びの乱れ、さらには頭痛や肩こりといった全身症状にまで影響を及ぼすこともあるため、放置せず早めの対策が肝心です。
マウスピースの装着やストレスケアといったセルフケアに加え、矯正歯科での相談やボトックス治療などの医療的アプローチを組み合わせることで、より効果的に症状を軽減することができます。
「もしかして自分も歯ぎしりをしているかも?」と感じたら、まずは歯科医院でのチェックを受けてみましょう。早期発見・早期対応が、将来のトラブルを未然に防ぐ第一歩になります。
当院はJR渋谷駅から徒歩4分、渋谷公園通り沿いにございます、渋谷以外では6医院関西大阪梅田、岸和田市、京都市、和歌山市に分院があります。
矯正治療実績は5000症例以上(※)あり、インビザラインではブルーダイヤモンドプロバイダーを受賞しております。
グループで矯正治療を管理しており、質の高い治療を提供しています。
東京・渋谷でインビザライン矯正・マウスピース矯正をお探しの方は一度無料相談(相談・精密検査費無料)にお越しください。
※2024年度グループ全体の矯正症例数
参考文献
Lobbezoo, F., Ahlberg, J., et al. (2018). Bruxism defined and graded: An international consensus. Journal of Oral Rehabilitation, 45(1), 3–7.
Manfredini, D., Winocur, E., et al. (2013). Epidemiology of bruxism in adults: A systematic review. Journal of Orofacial Pain, 27(2), 99–110.
American Academy of Sleep Medicine. (2021). Clinical practice guideline for the treatment of bruxism.
De la Hoz-Aizpurua, J. L., et al. (2011). Sleep bruxism. Systematic review of the etiology, diagnosis, and treatment. Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal, 16(2), e231–e238.
Emodi-Perlman, A., Eli, I., et al. (2020). Bruxism, psychological factors and temporomandibular disorders: A systematic review. Journal of Oral Rehabilitation, 47(5), 447–461.