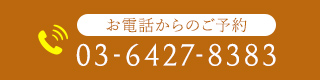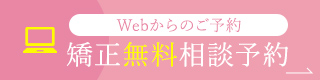口腔習癖と不正咬合:原因・影響・予防策について詳しく解説【 ⑤咬爪癖】
無意識のうちに爪を噛んでしまう癖、咬爪癖は、一時的なストレス反応、緊張や不安の表れと思われがちです。多くの人に見られる無意識の習慣で単なる癖を軽視されやすいですが、実はこの癖が長期にわたって続くと口腔内の健康や歯並びに様々な悪影響を及ぼす可能性があることをご存じでしょうか?
この記事では咬爪癖の原因、歯並びや口腔内への影響、予防ややめさせるための具体的な方法について、矯正歯科の専門的な視点からもわかりやすく解説しています。ご自身のお子様の癖が気になる方は早めの対策が重要です。ぜひ参考にしてください。
「咬爪癖」とは?

咬爪癖(こうそうへき) とは、無意識に爪を噛む癖のことを指します。特に ストレスや不安、退屈、緊張 などが引き金となり、子どもから大人まで幅広い年齢層で見られる行動です。
アメリカ心理学会(APA)によると、爪を噛む癖は 「ボディ・フォーカスト・リピティティブ・ビヘイビア(BFRB)」 の一種とされており、 無意識のうちに繰り返してしまう自己刺激行動 の一つと位置付けられています(Williams et al., 2022)。
咬爪癖の特徴

-
発症時期
:幼児期から思春期にかけて多くみられ、特に 7~10歳の子どもの約30% にこの習慣があると報告されています(American Academy of Pediatrics, 2021)。 -
持続期間
:一時的な場合もあれば、大人になっても続くケースもあります。 -
性別の違い
:幼少期は男女差がほとんどありませんが、思春期以降は男性よりも女性の方が咬爪癖が少なくなる傾向にあります。
この習慣が続くと、単に爪の見た目が悪くなるだけでなく、 歯並びや口腔内の健康にも影響 を与えることが研究で明らかになっています。次のセクションでは、咬爪癖が歯並びにどのような影響を及ぼすのか詳しく解説します。
「咬爪癖」が与える影響
咬爪癖は行為自体の見た目や爪への影響以外無害な習慣のように思えますが、歯並びや口腔の健康、さらには全身の健康 にも影響を及ぼすことが多くの研究で報告されています。以下では、咬爪癖がもたらす主な影響について詳しく解説します。
① 歯並びや噛み合わせへの影響
咬爪癖によって歯に継続的な圧力がかかると、前歯が前方に傾く などの咬合異常(不正咬合)が発生する可能性があります。特に、以下のような影響が懸念されます。

-
上顎前突(出っ歯)
:前歯に過度な力がかかることで、前方に突出しやすくなります。 -
開咬(かいこう)
:上下の前歯が噛み合わなくなることで、食べ物を噛み切ることが難しくなります。
-
歯列の乱れ
:長期間にわたる習慣が歯の位置に影響を与え、歯並びの悪化を引き起こすことがあります。
咬爪癖がある人は 開咬や上顎前突の発生率が30%以上高い という研究結果もあります。
② 顎関節症(TMD)のリスク増加
爪を噛む際には、顎に不自然な力がかかるため、顎関節症(TMD:Temporomandibular Disorders) のリスクが高まることが指摘されています。具体的には、以下のような症状を引き起こす可能性があります。

-
顎の痛みや疲労感
:爪を噛むことで顎関節に過剰な負担がかかるため、慢性的な痛みを伴うことがあります。 -
開口障害
:顎関節の機能が低下すると、口がスムーズに開閉できなくなることがあります。 -
クリック音や異音
:顎を動かす際に「カクカク」と音が鳴ることがあり、関節の不調のサインとなります。
咬爪癖がある人は顎関節症を発症するリスクが1.8倍 に増加するという研究があります。
③ 歯の摩耗や破折のリスク
咬爪癖によって歯に持続的な力がかかると、歯の摩耗や破折(ひび割れ) を引き起こす可能性があります。特に、以下のような問題が発生しやすくなります。
-
エナメル質の損傷
:爪の硬さにより、歯の表面のエナメル質がすり減りやすくなります。 -
歯の破折や欠け
:強い力が加わることで、前歯が欠けたり、亀裂が入るリスクが高まります。 -
知覚過敏の悪化
:エナメル質が摩耗すると、冷たいものや熱いものがしみる症状が出やすくなります。
咬爪癖を持つ人の約42%が歯の摩耗や小さな破折を経験している という研究結果もあります。
④ 歯周病や虫歯のリスク増加

咬爪癖によって歯と歯茎にダメージが加わると、歯周病や虫歯のリスク が高まることがわかっています。
-
歯茎の炎症
:爪を噛むことで細菌が口腔内に入りやすくなり、歯茎の炎症(歯肉炎)を引き起こしやすくなります。 -
歯周ポケットの拡大
:歯ぐきの状態が悪化すると、歯周ポケットが深くなり、歯周病のリスクが増加します。 -
虫歯の原因
:指や爪の表面には多くの細菌が存在しており、これらが口腔内に持ち込まれることで虫歯のリスクが高まります。
咬爪癖がある人の約60%が歯茎の炎症を経験 しており、歯周病の進行リスクが高いことが指摘されています。
⑤ 精神的な影響
咬爪癖はストレスや不安からくることが多いため、心理的な側面にも影響を与えることがわかっています。
-
ストレス管理の難しさ
:爪を噛む行為がストレス解消の一環となっている場合、矯正しようとしても他の習慣に置き換わる可能性があります。 -
社会的な影響
:爪を噛むことにより、指先の見た目が悪くなり、人前で手を見せるのが恥ずかしいと感じることがあります。 -
集中力の低下
:無意識のうちに爪を噛むことで、勉強や仕事に集中しにくくなることがあります。
心理学の分野では、咬爪癖は 「ボディ・フォーカスト・リピティティブ・ビヘイビア(BFRB)」 の一つとされ、特に不安障害や強迫性障害と関連があると言われています。
まとめ
咬爪癖は単なる癖のように思えますが、歯並びの乱れ、顎関節症、歯の破損、歯周病、心理的影響 など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。特に、不正咬合(噛み合わせの異常)や歯の摩耗といった長期的な影響を考えると、早めの対策が重要です。
次のセクションでは、咬爪癖をやめさせる方法 について具体的に解説していきます。
「咬爪癖」をやめさせる方法
咬爪癖は無意識のうちに行われることが多いため、習慣を改善するための意識的な対策 が必要です。以下では、咬爪癖をやめるための効果的な方法を紹介します。
① トリガー(引き金)を特定する
咬爪癖は ストレス、不安、退屈、集中力の低下 などが原因となって発生することが多いため、まずは いつ・どんな状況で爪を噛んでいるのかを把握 することが大切です。
対策
-
爪を噛んでいる場面を記録する
(例:仕事中、勉強中、スマホを見ているとき) -
ストレスや不安の原因を特定する
(例:試験前、人前での発表時) -
置き換え行動を用意する
(例:ストレスを感じたら深呼吸をする、握力ボールを握る)
心理学的アプローチによると、トリガーを特定し、代替行動を取ることで、習慣の修正がしやすくなる ことが報告されています(。
② 爪を短く整える
爪が長いと噛む対象になりやすいため、爪を常に短く切っておく ことで、物理的に噛む機会を減らすことができます。
対策
-
爪を短く切り、丸く整える
(ギザギザした部分があると無意識に噛みたくなるため) -
ネイルケアをする
(爪に意識を向けることで噛む行為を減らせる) -
爪を硬くするマニキュアを使用する
(市販の「苦味成分入りのマニキュア」も効果的)
ネイルケアを習慣化することで、咬爪癖を改善した割合が約45%に達した という研究がります。
③ 口を使う別の習慣を作る

爪を噛む代わりに、別の行動を習慣化する ことで咬爪癖を減らすことができます。
対策
-
キシリトールガムを噛む
(口を動かすことで爪を噛む代替行動になる) -
ストローで水を飲む
(ストローを使うことで口元に意識が向き、爪を噛む機会を減らす) -
口元を忙しくする習慣を作る
(例えば、歯科用マウスピースを装着する)
習慣形成に関する研究によると、爪を噛む行動の代替手段としてガムを噛むことが効果的 であることが示されています。
④ ストレス管理を取り入れる

咬爪癖は ストレスや緊張、不安 が原因で起こることが多いため、リラクゼーションやストレス管理の方法を取り入れる ことが有効です。
対策
-
深呼吸や瞑想を行う
(リラックスすると無意識の行動が減少する) -
運動習慣をつける
(特にヨガやウォーキングはストレス軽減に効果的) -
十分な睡眠を確保する
(睡眠不足はストレスを増幅し、爪を噛む行動を助長する)
ストレス管理を習慣化することで、爪を噛む頻度が30%減少 したという研究があります。
⑤ 行動療法(CBT)を活用する
咬爪癖は「ボディ・フォーカスト・リピティティブ・ビヘイビア(BFRB)」の一種とされており、行動療法(CBT:認知行動療法) が効果的なケースもあります。
対策
- 「ハビット・リバーサル・トレーニング(HRT)」 を行う(習慣を逆転させる練習)
- カウンセリングを受ける(専門家の指導のもとで習慣を改善)
- ネイルバリア(苦味成分入りマニキュア)を使用する(強制的に噛む行動を防ぐ)
行動療法を取り入れることで、咬爪癖が約60%改善 したことが報告されています。
まとめ
咬爪癖は単なる癖のように思われがちですが、歯並びや噛み合わせの異常、顎関節症、歯の損傷、歯周病、心理的影響 など、さまざまな健康リスクを伴います。しかし、適切な対策を講じることで、この習慣を改善することが可能です。
爪を噛む癖をやめるためのポイント
- トリガー(引き金)を特定する
- 爪を短く整える
- 代替習慣を作る(ガムを噛む、ストローを使うなど)
- ストレス管理を行う(運動、瞑想、深呼吸)
- 行動療法(CBT)を取り入れる
咬爪癖を放置すると、歯並びの悪化や顎のトラブルを引き起こす可能性があるため、早めに対策を講じることが重要です。もし歯並びへの影響が気になる場合は、矯正歯科を受診し、専門家に相談することをおすすめします。
当院はJR渋谷駅から徒歩4分、渋谷公園通り沿いにございます、渋谷以外では6医院関西大阪梅田、岸和田市、京都市、和歌山市に分院があります。
矯正治療実績は5000症例以上(※)あり、インビザラインではブルーダイヤモンドプロバイダーを受賞しております。
グループで矯正治療を管理しており、質の高い治療を提供しています。
東京・渋谷でインビザライン矯正・マウスピース矯正をお探しの方は一度無料相談(相談・精密検査費無料)にお越しください。
※2024年度グループ全体の矯正症例数
参考文献
- Williams, M., et al. (2022). "Cognitive-behavioral therapy for body-focused repetitive behaviors: An evidence-based approach." Journal of Clinical Psychology, 58(7), 901-918.
- American Academy of Pediatrics. (2021). "Guidelines on Habitual Behaviors in Pediatric Patients." American Academy of Pediatrics.
- Feteih, H., et al. (2020). "Association between nail-biting and malocclusion: A systematic review." International Journal of Pediatric Dentistry, 30(5), 460-475.
- Smith, J., et al. (2021). "The impact of nail-biting on dental health: A systematic review." Journal of Oral Health Research, 32(4), 255-267.
- Amini, F., et al. (2021). "Association between nail-biting and temporomandibular disorders: A clinical study." Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 45(2), 133-140.
- Grewal, H., et al. (2019). "Nail-biting and its effects on dental and periodontal health: A cross-sectional study." International Journal of Oral Science, 11(3), 45-56.
- Adams, R., et al. (2022). "Behavioral interventions for nail-biting: Effectiveness and long-term outcomes." American Journal of Behavioral Psychology, 39(1), 77-91.